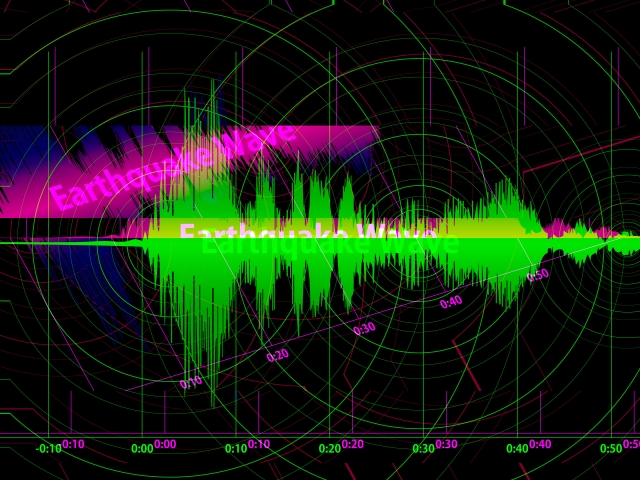【避難指示が出たら家にいてもいい?】在宅避難が認められる3つの条件と判断基準

「避難指示が出たけど、この家のほうが安全じゃない?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
大雨や地震のニュースが流れるたびに不安になる一方で、実際に避難指示が出ても「本当に出て行くべきなのか…」と迷う人は少なくありません。
実は、自宅の立地条件や備えが整っていれば「在宅避難(自宅避難)」が可能とされるケースもあるのです。
この記事では、「避難指示が出たときに家にとどまっていいか」を判断するための3つの条件や、ハザードマップの活用法、安全チェックの具体的な方法まで、わかりやすく解説します。
避難指示=絶対に移動、ではない。
状況によっては、動かないことが正解になるケースもあります。
その境界線を一緒に見極めていきましょう。

避難指示が出た場合でも、自宅にとどまる判断をしてもいいケースがあるのでしょうか?
本当に家にいたほうが安全なことってあるのか、正直わからないです。

条件さえ整っていれば、家のほうが安全なこともあるよ。
でも、それは「ちゃんと調べて備えてあること」が大前提。
なんとなくの感覚で決めるのはキケンだから、今からポイントをしっかり押さえていこう。
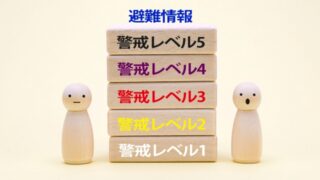
避難するべき?残るべき?「家のほうが安全」は本当に正しいのか

「避難指示が出ても、うちの周りは静かだし、むしろ外に出るほうが危ない気がします。
家にいたらダメなんでしょうか?」

気持ちはわかる。
実際、在宅避難が認められているケースもある。
ただ、それが通用するのは、家の安全性や災害リスクをきちんと把握できている場合に限るんだ。
その見極め方を紹介していくよ。
「在宅避難」が認められる3つの条件とは?
国が示す基準では、以下の3つすべてを満たしていれば自宅での避難が可能です。
🔹 自宅が倒壊や浸水の危険区域に入っていないこと
🔹 居室が浸水想定の深さより高い位置にあること
🔹 水・食料・トイレ用品など備蓄が十分にあること
これらはすべて、「避難しなくても命が守れる」ための最低条件です。
ただし一つでも欠けていれば、安全の保証はなくなります。
事前にハザードマップや自治体の情報を確認し、立地リスクや浸水深を把握しておくことが大切です。
備蓄に関しても、最低3日〜1週間分を目安にして備えておきましょう。
家が安全かどうかを見極める「判断基準」とは
自宅が本当に安全かどうかを判断するには、以下のような要素をチェックします:
・ 自宅が浸水想定区域、土砂災害警戒区域に入っていないか
・ 建物の構造や老朽化の有無(ひび割れ・傾き・外壁の劣化など)
・ 屋根やベランダ、排水口、塀などに異常がないか
・ 周囲に倒壊しそうな建物や火災のリスクがないか
感覚ではなく、データと目視点検を合わせて判断することが重要です。
不安な場合はホームインスペクターなど専門家に診断を依頼するのも安心材料になります。
自宅の安全性は「家の中だけ」を見てもわかりません。
周辺環境や地盤、避難経路の有無まで総合的に確認することが、安全を守るポイントです。

ハザードマップはどう使う?「うちは安全」と思い込む前に見るべき情報


ハザードマップを見れば安心ってよく聞きますが、どこをどう見ればいいのかわかりません。
地図に色がついていても、意味がわからなくて…。

確かに、ただ色がついているだけだとピンとこないよね。
でも、正しく見れば“逃げるべきかどうか”が判断できるヒントになるんだ。
使い方のコツを伝えるよ。
浸水リスク・土砂災害リスクの見方を知る
「重ねるハザードマップ」や自治体の防災マップでは、次のリスクが表示されています:
・ 浸水の想定区域と深さ(○メートルと記載あり)
・ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域
・ 津波・高潮の到達範囲
浸水深が2メートル以上などのエリアでは、1階部分は完全に水没する恐れがあります。
その場合、2階以上に安全な部屋があっても、建物自体が流される可能性もあり非常に危険です。
「色が薄いから大丈夫」ではなく、数字と範囲を確認し、「どこまで危険なのか」を把握することが重要です。
火災や地盤崩壊など「地図に出ない危険」も考慮する
ハザードマップに載っていない危険もあります。
たとえば:
・ 老朽化した木造密集地域に住んでいる場合の延焼リスク
・ 大規模盛土造成地など地盤が崩れやすいエリア
・ 近隣の工場や倉庫からの火災・爆発など
マップは参考資料のひとつであって、絶対の判断基準ではありません。
地域の特徴や過去の災害記録、周辺施設の状態まで見ておくことで、より現実的な判断ができます。
地図だけでは見落としがちなリスクもあるため、近所の人や自治体と日頃から情報を共有しておくことも、防災対策の一つになります。

備えがあるから大丈夫」は本当?自宅避難に必要な“見えない条件”

備蓄もしてあるし、家もなんとなく安全そうなので、うちは避難しなくても大丈夫だと思っています。
この認識って合っていますか?

その「なんとなく」がいちばん危ないかも。
備蓄や設備があっても、それだけじゃ安全とは言い切れないんだ。
確認すべきポイントを紹介するね。
室内の安全確保ポイントとは?避難生活を支える工夫
自宅で避難生活を送るには、家具の固定や安全な居場所の確保が重要です。
・ 倒れそうな家具の前で寝ない
・ 窓から離れた位置に寝る
・ ガラス飛散防止フィルムを貼っておく
・ トイレや簡易トイレの準備をしておく
「ただ家にいる」だけではなく、安全に生活できる空間を整えておくことが前提です。
水・食料に加え、ライト・電池・充電器・ポータブルトイレなど、避難所と同じような環境を想定しましょう。
専門家に頼る“住宅診断”という選択肢
地震や風水害の後に自宅のダメージに気づく人は多くいます。
その前にできる対策が「住宅診断(ホームインスペクション)」です。
・ 基礎のヒビ割れや傾斜
・ 雨漏りのリスク
・ 給排水管の破損や老朽化
・ 換気設備や排煙装置の点検
住宅診断は数万円〜受けられ、安全性を客観的に評価できます。
特に古い家に住んでいる場合や、大雨・地震の多い地域では検討の価値があります。
点検をしてみて、初めて「意外と危なかった」と気づくこともあります。
判断に迷う方は、プロに相談することも安全の第一歩です。

まとめ
避難指示が出たら原則は避難所へ向かうべきですが、「家にいたほうが安全」という選択も絶対に間違いとは言えません。
ただし、それには条件があります。
・ 自宅が災害想定区域外であること
・ 建物や周囲の安全が確認されていること
・ 備蓄や室内環境が整っていること
この3点が揃って初めて、「自宅避難」も一つの選択肢になります。
感覚や経験則ではなく、データと実際の備えをもとにした判断が、命を守るカギになります。
今のうちに、自宅の安全性を見直してみませんか?